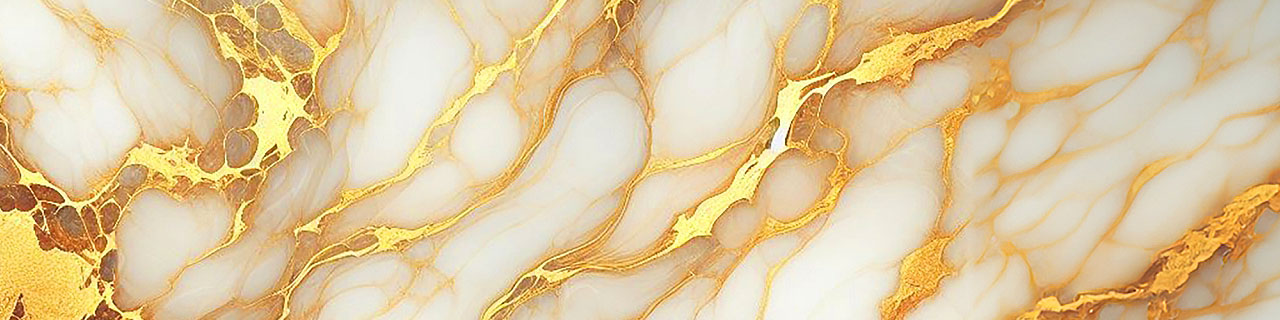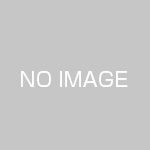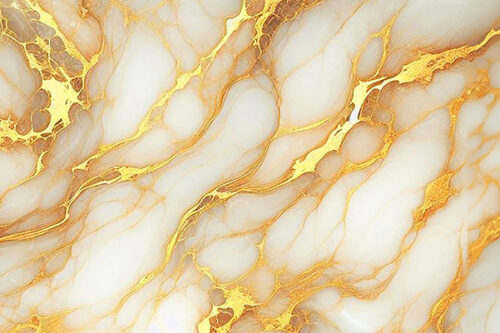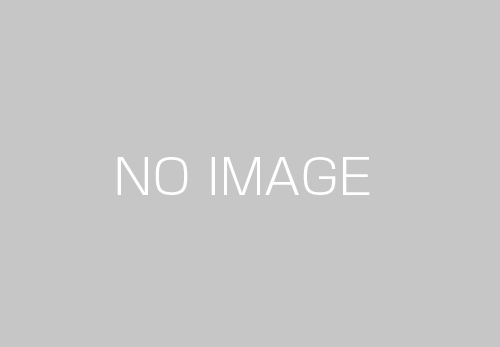◆父の遺言を守る旅:ガダルカナル島で散骨した忘れられない5日間
〇父、釣部二郎との思い出
2007年11月12日、私の父、釣部二郎は89歳でこの世を去りました。父がガダルカナル島(以下、ガ島)から生還したことは、私たち家族にとって非常に重要な出来事でした。彼は戦後も何十年も、戦争の記憶に囚われていたように思います。鼓膜が爆撃で破れ、酒を飲むといつも声が大きくなり、戦争の思い出が口をついて出ました。特にガ島での壮絶な戦闘や生き残るための過酷な撤退行軍、そして仲間を失った悲しみは、彼の中で深く刻まれていました。イル川での戦いや、アウステン山での米軍との激戦、エスペランス岬への死の行軍、撤退作戦の成功など、父はいつも同じ話を繰り返し語っていました。その話の最後には、決まって「甲板で見た南十字星は、本当にきれいだった」という言葉が添えられていました。
父が戦争から帰還した後、彼の人生に大きな影響を与えたのがカトリック教会との出会いでした。彼は戦後すぐにカトリックの洗礼を受け、その後も教会に多額の寄付を行い、土地を提供して幼稚園を作ろうとまでしました。特に印象的だったのは、ドイツから来た神父さんに車を提供したことです。戦争で心に深い傷を負った父が、戦後は他者への奉仕を通じてその傷を癒そうとしていたことが感じられました。
しかし、父の思い出話は、常にガダルカナル島での戦いから始まり、そこに戻っていくようでした。何十年も経過しても、その記憶が彼の中で更新されることはなく、戦争が彼に与えたトラウマは癒えることがなかったのだと思います。特に「俺が死んだら、遺骨をガ島に散骨してくれ」という遺言は、私たち家族にとっても重く響く言葉でした。2018年11月、父の遺言を実行するために私は妻と共に、ガダルカナル島への散骨旅行を決意しました。これは単なる旅行ではなく、父の魂を戦友たちのもとへ送り届けるための重要な旅でした。
ガダルカナル島への旅:父の遺言を実行する日
12月16日、私たちは父の遺骨を携え、サッポロビールと父の軍服姿の写真を持って、ガダルカナル島へ向けて出発しました。ポートモレスビーを経由し、ホニアラに到着したのは翌日のことでした。ホニアラ国際空港(元ヘンダーソン飛行場)は、父が戦時中に奪回を試みた場所であり、その地に立つことで父がどんな思いでこの飛行場を見つめていたのかが胸に迫りました。
現地では、ガイドのフランシスが私たちを出迎えてくれました。彼はカトリック教徒で、日本にも留学経験のある45歳の男で、片言の日本語と英語を交えながら、私たちに戦地を案内してくれました。初めに訪れたのは、一木支隊が壊滅したイル川河口、通称「アリゲータークリーク」でした。この場所は父が何度も話していた場所であり、ここで一千人近い日本兵が命を落としたという話は、現地でフランシスの説明を聞きながら改めて実感しました。私は流木に父の写真を立てかけ、サッポロビールと線香を供え、遺骨を散骨しました。「一木支隊の皆様、釣部二郎を連れて参りました」と心の中で祈りながら、戦友たちに父の遺骨を捧げました。
その瞬間、私は父が戦争でどんな思いを抱えていたのかを深く理解しました。私が子供の頃、父に「戦争で人を殺したことがあるのか?」と聞いたことがありました。その時、父は淡々と「弾丸が飛んでくるジャングルに向かって撃つしかなかった。そうしなければ自分が死ぬんだ」と答えました。その時の父の表情は今でも鮮明に覚えています。彼が感じたであろう葛藤と恐怖、そして生き延びるための戦いが、彼の言葉に重く宿っていたのです。
〇父の親友との最後の別れ
父が最も辛かった戦争の記憶の一つは、親友の自決でした。ガ島での撤退行軍中、体力を失い歩けなくなった親友は「もう置いていってくれ」と父に告げ、自ら命を絶ったのです。父はその時のことを涙を流しながら語っていました。父が戦場で涙を見せたのは、この一度きりだったと思います。戦友たちが次々と倒れていく中で、父は自らも死と隣り合わせで戦っていたのです。
この親友の命を絶った場所もまた、私たちが訪れたガ島の一部でした。私は、そこに眠る父の親友に向けて手を合わせ、彼の魂に祈りを捧げました。今もガ島のジャングルの中には、父のように祖国に帰ることができなかった多くの日本兵の遺骨が眠っています。私の中には、この戦地で命を落とした多くの兵士たちへの思いが強く湧き上がってきました。
〇エスペランス岬:最後の撤退
最終的に私たちは、日本軍が最後に撤退したエスペランス岬にも足を運びました。父はこの場所で戦い、撤退作戦が成功した時には、戦友たちと甲板で南十字星を見上げたと語っていました。その南十字星は彼にとって、祖国への希望の光であったのでしょう。
ガ島の自然は今も変わらず、静かな波が寄せては返していました。その風景の中で、私は改めて父がこの地でどんな思いを抱いていたのかを感じました。撤退作戦の成功は、父にとって奇跡のような出来事であり、祖国に生還できたことへの感謝と喜びが彼の心の中にあったのだと思います。
〇父の信仰:なぜカトリックを選んだのか
散骨の旅の最後、ガイドのフランシスは私たちをカトリック教会に案内してくれました。そこには、戦時中に日本兵を救ったシスターたちがいて、多くの兵士がここで食事を提供され、命を救われたといいます。父がカトリックの洗礼を受け、教会に深い信仰を寄せていた理由が、ここで初めて明らかになった気がしました。戦争で命を救ってくれたシスターたちに対する感謝の念が、父の中に強く残っていたのでしょう。
帰国後、父が教会に多額の寄付を行い、幼稚園を作ろうとまでした背景には、このような感謝の気持ちがあったのだと思います。彼はただの信者ではなく、戦争で受けた傷を癒すために、他者への奉仕を通じて自らを支えていたのです。カトリックと仏教が共存する我が家の不思議な光景も、父の価値観や信仰が形となって現れていたのだと、今になって思います。
〇父の選んだ信仰:なぜカトリックだったのか
ガイドのフランシスが連れて行ってくれた現地のカトリック教会は、ただの教会ではありませんでした。そこには、父が戦時中に命を救われた背景が詰まっていました。撤退の際、ほとんどの日本兵は疲れ切り、歩くこともままならなかったといいます。その時、現地のカトリックのシスターたちが、食事や休息を提供し、命を救ってくれたのです。敵国の兵士であろうと、彼らは人道的な救済を行い、その行為が父にとってどれだけ大きな意味を持ったのか、改めて実感しました。
父が帰国後、カトリック教会に通い続けたのは、この時の経験が根底にあったのでしょう。彼は単なる信者としてではなく、命を救ってくれた人々に感謝し、恩返しの一環として教会に多額の寄付をし、さらには幼稚園を建てようとまでしました。彼にとって、信仰は単なる宗教的な教えに留まらず、命を救ってくれた存在への深い感謝の表れだったのです。この経験が彼の人生観を大きく変え、カトリックの教えを信じることで彼の心の中の戦争の傷を少しでも癒していたのではないかと感じます。
家にあった仏壇とカトリックのマリア像が並んでいるという光景は、私にとっては不思議なものでした。しかし、父にとってはそれが当たり前であり、彼の信仰の形だったのです。戦争を通じて感じた「神様はケンカしないけど、人間は差別して戦争をする」という父の言葉は、まさにその通りであり、彼は宗教や民族に関わらず、人々を平等に見る心を育んでいたのでしょう。だからこそ、父はカトリックを選び、他者への奉仕を通じて自らを支えていたのだと感じます。
フランシスは、私の話を聞きながら黙って微笑んでいました。彼もまた、現地で戦争の歴史を伝える重要な役割を担っている一人であり、彼の案内は私にとって非常に心強いものでした。
〇散骨の旅の終わりと父とのつながり
三泊五日のガダルカナル島での散骨の旅は、私にとって非常に大きな意味を持つものでした。父の遺言を実行し、彼の魂を戦友たちのもとに送り届けるという大切な使命を果たすことができたからです。散骨を終えた後、私は父と初めて深くつながった気がしました。これまで理解できなかった父の思いや、戦争で彼が抱えていた苦しみが、この旅を通じて少しずつ見えてきたのです。
父が遺言で「俺のことを知りたかったら、ガダルカナル島に散骨に行けばすべてわかる」と言っていたのは、決して誇張ではありませんでした。彼が伝えたかったのは、戦争の恐怖や悲惨さ、そして戦後の生き残った者たちが抱える深い悔恨や孤独感だったのです。戦友たちがどれだけ無念の思いでこの世を去っていったのか、生き残った者がどれだけその記憶に苦しんだのか、ガ島に立つことで初めて実感しました。
また、父の「戦争の原因は宗教や民族ではなく、差別だ」という言葉が、現代社会においても通じる普遍的なメッセージであることに気付きました。人間は差別や憎しみから戦争を引き起こし、多くの無実の命が犠牲になる。そのことを次世代に伝えることが、父の望みだったのかもしれません。彼は、戦争の悲惨さを後世に伝え、再び同じ過ちを繰り返さないようにと願っていたのでしょう。
ガダルカナル島での散骨が終わり、帰国の準備をしていた朝、ベランダに一羽の鳥がやってきました。私がベランダに出ても、その鳥は逃げることなく、ただ私を見つめていました。それはまるで父が「ありがとう、よくやった」と言ってくれているかのような気がしてなりませんでした。
帰国の飛行機の中で、父が「ガ島で死んだ兵士は、米軍に殺されたのではなく、大本営に殺されたんだ。国家にとって俺たちは虫けらなんだ」と言っていた言葉を改めて噛みしめました。国家の犠牲となり、若者たちが戦争に駆り出され、多くが命を落とした。その事実を忘れてはならないと強く感じました。
帰国してから数日が経ち、アリゲータークリークの海岸で拾ってきたサンゴの石を仏壇に置きました。父の遺影に向かって無事の帰国を報告し、私の三泊五日の慰霊と散骨の旅は静かに幕を閉じました。父がガ島で見た南十字星が、私の心の中でも永遠に輝き続けることを感じながら。